流れる星は生きている
(藤原てい著 中公文庫)
生きる、ということは命をつなぐことか!(寺岡 晟)
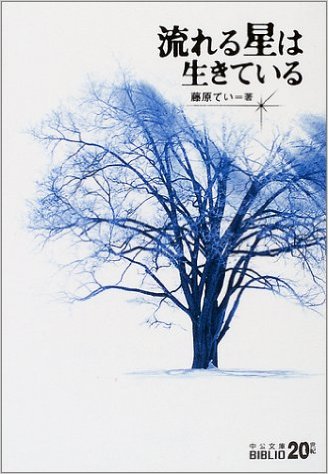
(藤原てい著 中公文庫)
生きる、ということは命をつなぐことか!(寺岡 晟)
『「正広ちゃん、正彦ちゃん、あしたの朝上陸するんですよ、そしてお汽車に乗っておばあちゃんの処へ帰れるんですよ」
私は両手に二人を抱きしめて、ほんとのことを言える嬉しさに頬が赤くなるほど嬉しかった。
…中略
妙に感傷的になって私は仰向けになったまま眼を軽く閉じると、流れるように私の唇をついて出て来るのは北朝鮮の丘の上で歌った『流れる星は生きている』のメロディであった。
いつかあなたに逢える
きっとあなたにまた逢える
ご覧なさいね 今晩も流れる星は生きている
口の中で低く繰り返し繰り返し歌っていると涙の糸が頬を伝い、耳朶を伝い、船倉の床まで細く細く続いていた。
そして自分自身がだんだん浄化されていくように落ち着いてくると、私は夫が傍にいる時のように久しぶりで安らかな眠りに入っていった。』
この「流れる星は生きている」の著者、藤原てい氏の満州からの引き揚げの実体験に基づいて書かれた小説である。
彼女の夫は、有名な小説「八甲田山死の彷徨」を書き下ろした作家新田次郎氏の妻だ。
と言いながら、実は僕は彼女、藤原てい氏のことをまったく知らなかったのである。
昨年(2016年)の11月のことだった。
新聞の訃報欄に「藤原てい氏死去」という記事に眼が止まり、記事を読み進むに従って
新田次郎氏の妻だったこと、戦後、標題の「流れる星は生きている」を著作し、当時のベストセラーになり、映画や後にはテレビドラマ化され、この時代の人ならば誰でも知っている有名な本だったそうだ。
また、お二人の間に生まれ、母ていと共に決死の旅を歩んだ次男は「国家の品格」の著者藤原正彦氏だということも、そのとき知った。
僕は、故新田次郎氏のファンだったこともあり、この「流れる星は生きている」を読んでみようと思い立ち、手にした訳だ。
内容はこうだ。
戦前、気象台勤務だった夫(新田次郎氏)と共に当時の満州(現中国東北地区)の
新京(長春)にいた著者が、8月15日の終戦直後に不可侵条約を踏みにじって満州になだれ込んで来たソ連軍から逃れるため、仕事のある夫と別れ、3人の子どもを連れて、満州(中国東北部)から危険な目に何度も会いながら、満州から北朝鮮を経て、朝鮮半島の38度線を越え、アメリカ軍に保護され、その後、釜山から引き揚げ船にのり博多へたどり着いた。
冒頭に挙げた文は死地を脱して、引揚船に乗って博多港に着き、日本上陸前夜の著者の心境を記したものだ。
それまでの凄まじいまでの行動を読んだ僕は、そのときの著者の気持ちが少しは汲み取れたように感じられ、心の平安が訪れた情景が目に浮かんだ。
慌ただしく新京の駅頭で、仕事で残ることになった夫と涙で別れ、当時長男の正広さんは6歳、次男の正彦さんは3歳、長女の咲子さんは生後1か月でした。
それまで夫に頼ることが全てだった著書は「何としてでもこの子らを日本に連れて帰る!」と悲壮な決心をして、脱出行が始まった。
このような極限状態では、人間の持つエゴと優しさが表面化してくる。
著者はそのような環境の中で、生きるために、子供たちを無事に連れて帰るために必死で
戦っていく。
読み進んでいくと、最初はお嬢様育ちの苦労知らずの奥様のようだった著者が荒波にもまれていく過程で、たくましくなり、生きる知恵が芽生え、そして毅然と困難に立ち向かっていく姿に「頑張れ!負けるな!」と、応援しながら読み進んでいった。
人間はここまでになっても気力があれば生きられるのか。
食糧不足で子供たちは、みんな栄養失調状態となり、次々と周りの子供たちは死んでいきます。
このときの3人の子供を生かして行くんだという母親の執念は、それは凄いものです。
しかし、他の母親は自分の2人の子供を生かすために、小さい赤ちゃんをあきらめるという選択をする人も出てきて、中には子供を欲しがる朝鮮人に僅かばかりの食糧とお金で売り渡す人も。
そのことを非難することは容易いことだけど、その場にいれば、断腸の思いでそうせざるを得ないかも知れない。
どちらの選択においても、生きている命をつないで行くということは、言葉では説明しがたい迫力で迫ってきた。
北朝鮮の平穣を超え、38度線に近づいて来たときの頃です。
『汽車は新幕に到着した。貨車を開けると外から横なぐりに雨がさっと吹き込んできた。貨車から降りると外は暗闇で自分の子供の顔さえ分からない風雨の中であった。「しいッ!」という男の声がどこからか聞こえてきた。
「これから最も危険な場所を夜通し歩きます、出来るだけ荷物を軽くして前の人を見失いように急いで歩くのです。すぐ出発します、すぐ出発しますよ!」
その声は風雨の中に低く恐ろしい響きを持って伝わって来た。
「列から離れた人は置いて行かれますよ、前の人を見失わないように、落後したらおしまいですよ」また例の声が地の底から湧いて来るように聞こえる。
私はこの声を誰が出しているか知らない。
だがこの日本人の群集の中にリーダーがいることだけは確かだ。
ここで私は缶詰めを全部捨て、炒ってない大豆を捨て、自分の荷物を半分ほどにした。誰かが用意の提灯に火を灯したらしい、その辺りがうす明るくなった。
「火を消せ!」
鋭い声が矢のように飛んで来て、その火を吹き消した。
人間の塊は動き出した。
私は右手に正彦を抱きかかえ、左手に正広の手を持って、咲子を背にリュックを首にぶら下げて人の群れを追った。
…・中略
正広は間もなく、めそめそ泣きだした。
「お母ちゃん、歩けない」
正広のことなんかかまっていられない。
私は正彦を十歩は抱いて歩き、十歩は手を持って引きずって行った。
背中の咲子と頭に吊った荷物が雨に濡れて重くなって来た。
雨は背中までとおり、はいていたズボンがずり落ちそうに重かった。
肩に食い込む重みと、頸をもぎ取ろうとするリュックが私の身体を何遍も土にまみれさせた。
私は前の影を負うことだけしか考えない。
頭の中が妙に空白になっていながら前進するということだけが激しく私を支配して、歯を食いしばり、正広と正彦をどなりつけていた。
「正広、なにをぐずぐずしている!」
「正彦、泣いたら、置いていくぞ!」
私はこの時初めて男性の言葉を使っていた。
自覚しないで私の口をついて出てくるものは激しい男性の言葉であった。
道が坂になった。
二歩登っては、一歩すべる、正彦が<ひいッ!ひいッ!」と泣く声が風にちぎれて飛んでゆく。
私は正彦の尻を力いっぱいたたきながら、よろける正広をどなりつけて登っていった。』
その時の親子の情景というより格闘が目に浮かぶ。
著者は、こうやって戦争を、そして苦難を乗り切ってきたんだと、改めて思った。
あとがきにこう記されている。
『引き揚げて来てから、私は長い間、病床にいた。それは死との隣り合わせの
ような日々であったけれども、その頃、3人の子供に遺書を書いた。
口に出してなかなか言えないことだけれども、私が死んだ後、彼らが人生の岐路に立った時、また、苦しみのどん底に落ちた時、お前たちのお母さんは、そのような苦難の中を、歯を食いしばって生き抜いたのだということを教えてやりたかった。
そして祈るような気持ちで書き続けた。
しかし、それは遺書にはならなかった。
私が生きる力を得たからである。
それがこの本になった。』
生きる、ということは命をつなぐことか!
この「流れる星は生きている」を読んだ私が見出したことだ。
